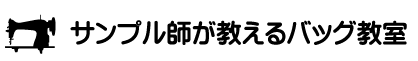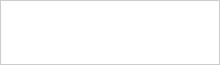いつまでも『下働き』させられている理由
投稿日 : 2019年2月17日
最終更新日時 : 2019年2月17日
投稿者 : nakamura
カテゴリー : 思い出話
かばん作りの技術を習得するつもりでいてるのに、
来る日も来る日も『糊付け機』に向かって
ひたすらゴム糊を塗り続けていたのでは何も覚えられない
なんて思っていませんか?
ゴム糊を塗り続けているだけではありません、
糸切りもそうです。
運動会の万国旗のように連なったパーツの糸切りばかりしてもなにも覚えられない
下仕事は他にもありますが
何れにしても慣れれば手が覚えて
ある程度、
よそ見をしながらでも出来るんですね
。
この『よそ見』なんですが
何処を『よそ見』するかが重要で、
まわりの人の動き、仕事の流れを
この作業の中で見て覚えていくのです
。
材料が入ってきたな、
パーツ毎に色々な人に振り分けているな、
どのパーツが真っ先に自分のトコロにくるのかな、
自分の仕上げた仕事は次に誰のトコロにいくのかな、
あんな風にミシンがけをするんだな、
ミシンの交換パーツはあの引き出しだな、
ミシンの下糸のなくなると音が変わるんだな、
下糸のなくなりかけにも音の変化があるんだな、
荷造り紐はあんな風に結ぶんだな
、
などなど、
色々な事をシュミレーション出来ます
。
ですから時々くるチャンス
「ちょっとココだけミシンがけをしてくれ」
に対応しやすくなるのです
。
ですから下仕事ばかりさせられて、
誰も自分の事を見てくれないと思うのは
大方は間違えかと思うんですね
。
まわりの先輩たちは、
新人を見るまでもなく
仕事のリズムを聞けば
どの程度はかどっているのかが分かっています
。
糸切りで例えると、
小バサミの音が一定間隔で聞こえますよね。
それで作業が早いか遅いが判断できます。
早くなっても気づきますし、
手が止まっていても気付きます。
一定間隔で聞こえてくるのが当たり前のところに
一定じゃない間隔で聞こえれば
変じゃないですか、気持ち悪く感じますよね
。
例えが遠くなりますが、
木魚の音が一定間隔で聞こえてくるのは普通ですが
不安定なリズムで聞こえると
気持ち悪く感じませんか
。
そんな感じで
この仕事は手を動かしながら
耳から色んな情報を入れてるんですね。
関連
Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/ccrui/www/bagsample/bagsample2/wp-content/themes/biz-vektor/single.php on line
47
アーカイブ アーカイブ
月を選択
2026年2月 (3)
2026年1月 (4)
2025年12月 (5)
2025年11月 (2)
2025年10月 (8)
2025年9月 (5)
2025年8月 (3)
2025年7月 (1)
2025年6月 (6)
2025年5月 (9)
2025年4月 (7)
2025年3月 (4)
2025年2月 (3)
2025年1月 (6)
2024年12月 (2)
2024年11月 (3)
2024年10月 (4)
2024年9月 (7)
2024年8月 (2)
2024年7月 (2)
2024年6月 (3)
2024年5月 (6)
2024年4月 (4)
2024年3月 (4)
2024年2月 (1)
2024年1月 (6)
2023年12月 (1)
2023年11月 (5)
2023年10月 (2)
2023年9月 (3)
2023年8月 (5)
2023年7月 (8)
2023年6月 (3)
2023年5月 (6)
2023年4月 (6)
2023年3月 (4)
2023年2月 (1)
2023年1月 (4)
2022年12月 (6)
2022年10月 (3)
2022年9月 (2)
2022年8月 (2)
2022年7月 (3)
2022年6月 (3)
2022年5月 (1)
2022年4月 (5)
2022年3月 (1)
2022年2月 (3)
2022年1月 (5)
2021年12月 (2)
2021年11月 (2)
2021年9月 (3)
2021年8月 (2)
2021年7月 (1)
2021年6月 (2)
2021年5月 (2)
2021年4月 (2)
2021年3月 (2)
2021年2月 (3)
2021年1月 (3)
2020年12月 (1)
2020年11月 (4)
2020年10月 (2)
2020年9月 (4)
2020年8月 (4)
2020年7月 (5)
2020年6月 (5)
2020年5月 (7)
2020年4月 (3)
2020年3月 (5)
2020年2月 (3)
2020年1月 (4)
2019年12月 (4)
2019年11月 (4)
2019年10月 (1)
2019年9月 (5)
2019年8月 (10)
2019年7月 (3)
2019年6月 (8)
2019年5月 (4)
2019年4月 (8)
2019年3月 (6)
2019年2月 (7)
2019年1月 (1)
2018年12月 (4)
2018年11月 (5)
2018年10月 (4)
2018年9月 (4)
2018年8月 (5)
2018年7月 (1)
2018年6月 (4)
2018年5月 (4)
2018年4月 (4)
2018年3月 (1)
2018年2月 (8)
2018年1月 (2)
2017年12月 (10)
2017年11月 (13)
2017年10月 (15)
2017年9月 (10)
2017年8月 (12)
2017年7月 (10)
2017年6月 (13)
2017年5月 (16)
2017年4月 (14)
2017年3月 (14)
2017年2月 (14)
2017年1月 (15)
2016年12月 (7)
2016年11月 (7)
2016年10月 (15)
2016年9月 (7)
2016年8月 (13)
2016年7月 (6)
2016年6月 (10)
2016年5月 (12)
2016年4月 (13)
2016年3月 (11)
2016年2月 (12)
2016年1月 (12)
2015年12月 (16)
2015年11月 (3)
2015年10月 (9)
2015年9月 (11)
2015年8月 (6)
2015年7月 (5)
2015年6月 (9)
2015年5月 (5)
2015年4月 (9)
2015年3月 (5)
2015年2月 (5)
2015年1月 (4)
2014年12月 (11)
2014年11月 (4)
2014年10月 (5)
2014年9月 (7)
2014年8月 (6)
2014年7月 (4)
2014年6月 (7)
2014年5月 (11)
2014年4月 (7)
2014年3月 (18)
2014年2月 (13)
カテゴリー